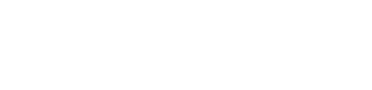
ジャーナルクラブ
抗炎症性サイトカインであるIL-10は、活性化された免疫細胞によって産生され、免疫応答を制御する上で重要な役割を担うことで知られている。しかし、その作用のメカニズムはほとんど分かっていない。本論文において著者らは、IL-10が炎症刺激によって誘導されるマクロファージの代謝の切り換えを阻止することを明らかにした。特に、IL-10はリポ多糖によって誘導されるグルコースの取り込みや解糖系を抑制し、酸化的リン酸化を促進することを示した。さらに、IL-10は、mTOR阻害分子であるDDIT4の誘導を介してmTORの活性化を抑制する。結果的に、IL-10はマイトファジーを促進し、膜電位の低下や活性酸素の増加に特徴づけられる機能不全のミトコンドリアを除去する。IL-10シグナルの欠損は、腸炎モデルマウスや炎症性腸疾患患者においてマクロファージ内に障害を受けたミトコンドリアを蓄積し、この結果、NLRP3インフラマソームの活性化やIL-1β産生といった調節不全を引き起こす。
フェロトーシスは、グルタチオンペルオキシダーゼ4欠損によって起こる細胞死の1つであり、直接的な実行因子として過酸化脂質が考えられている。しかしながら、フェロトーシスが過酸化脂質によって誘導されるという直接的な証拠、過酸化脂質の化学構造およびフェロトーシス誘導経路は明らかにされていない。本論文では、アラキドン酸(AA)やアドレン酸(AdA)を脂肪酸側鎖として有するホスファチジルエタノールアミンの酸化体が細胞内に蓄積することでフェロトーシスを引き起こすということを明らかにした。
骨髄における造血前駆細胞の動的挙動については解明されていない。本論文では、高解像度の共焦点レーザー顕微鏡を用い、造血ストレスと白血病時の顆粒球/マクロファージ前駆細胞(GMP)の動的挙動を追跡した。定常状態では、GMPは骨髄全体に散在していた。一方、造血ストレスおよび白血病時は、骨髄内にGMPクラスター(cGMP)を形成し、cGMPから顆粒球が分化した。このcGMP形成は、内的要因(IRF8およびβ-カテニン)と外的要因(骨髄ニッチシグナル)により制御されていた。今回の結果により、これまで認識されていなかったGMPの動的挙動が in situ で明らかになった。また、この動的挙動が造血ストレスや白血病時の骨髄造血や病態形成に重要な役割を果たしていることが明らかとなった。
脳脊髄液を介した軟髄膜転移は乳がんや肺がんの患者で起こりやすく、転移場所にアクセスしにくいことから治療が困難な症例である。軟髄膜への転移は脳脊髄液中にがん細胞が浸潤•増殖することで起きるが、低栄養環境の脳脊髄液でなぜ転移が成立するのか今日まで明らかではなかった。本論文で筆者らは、1)高確率に軟髄膜転移を起こす乳がん及び肺がん細胞株で補体のC3が高発現していることを見出した。2)がん由来のC3は血管と脳脊髄液を隔てている脈絡上皮細胞膜上のC3aRに作用し、バリア機能を喪失させることを証明した。3)その結果、脳脊髄液中に血管由来の成長因子が流入し、がんの増殖が活発になったが、C3aRのアンタゴニストを投与すると転移が劇的に改善した。本論文で筆者らは低栄養環境における転移の成立メカニズムを示し、C3シグナリングを標的とした新たながん転移に対する治療戦略を提唱した。
マクロファージの脂肪酸代謝は、炎症の進展に伴いダイナミックに変化するが、脂肪酸合成の制御機序や炎症調節における意義はくわしく分かっていない。この論文で著者らは、脂肪酸合成酵素の発現が炎症の急性期には一過性に減少するものの、終息期にはむしろ増加することに着目した。そしてTLR4下流のシグナルが炎症の後期にSREBP1を活性化し、そのSREBP1が抗炎症作用を持つ不飽和脂肪酸の合成を促進し、炎症を負に制御することを明らかにした。以上の結果から著者らは、SREBP1依存的な不飽和脂肪酸合成が、炎症の適切な終息に重要であると主張する。
アポトーシス細胞は、自身のクリアランスを促すためにfind-meシグナルを放出する。そのようなシグナルの一つ、スフィンゴシン1-リン酸(S1P)はマクロファージのS1PR1に結合し、HIF-1a依存的にエリスロポエチン(EPO)の産生を誘導する。EPOはマクロファージ自身のEPO受容体(EPOR)に結合し、その下流のシグナルがMFGE8, MERTK等の死細胞受容体発現を増加させることでマクロファージによる死細胞クリアランスを促進する。マクロファージ特異的EPOR欠損マウスはループス様自己免疫疾患を自然発症することから、EPOによる死細胞クリアランスの亢進が免疫寛容維持に重要なことが証明された。
Nrf2は酸化ストレス応答を司るマスター転写因子である。以前から、Nrf2が炎症疾患抑制にも重要な役割を担うことが知られていたが、あくまで酸化ストレス抑制に伴う副次的な効果だと考えられていた。本論文で著者らは、Nrf2がLPS+IFN刺激に対するマクロファージの免疫応答を抑制すること、そしてこの抑制が活性酸素種の消去に伴う2次的な現象ではないことを示した。さらにNrf2恒常的活性化マウス(Keap1欠損マウス)ではEAEの臨床症状が改善することを示し、Nrf2の炎症抑制機能を生体レベルで証明した。
この論文の著者らは、LC3-associated phagocytosis(LAP)の異常が自己免疫疾患の原因となる、と主張している。LAPは、著者らの見出したファゴサイトーシスの様式で、オートファジー経路の一部を利用して貪食物質を分解するのが特徴である。貪食したparticleにTLR2やFc受容体のリガンドが存在すると、Rubicon-NOX2-LC3依存的にファゴソームとライソソームが融合し、内容物が分解される。NOX2欠損マウスでは、血清自己抗体価の上昇、補体・免疫複合体の沈着を伴う進行性の腎機能障害を自然発症したことから、LAPが自己寛容の維持に重要なことが分かった。
この論文の著者は、交感神経活動が免疫細胞(消化管筋層マクロファージ)の形質制御に関与することを報告した。消化管の粘膜と筋層には形質の異なるマクロファージ亜集団が局在する。筋層のマクロファージが炎症促進的形質を示すのに対し、粘膜の亜集団は組織保護的形質を示す。腸内細菌は消化管筋層を走る交感神経からのノルアドレナリン分泌を促進し、これが筋層マクロファージの組織保護的遺伝子発現を誘導する。すなわちノルアドレナリンが筋層マクロファージの形質を制御する環境シグナルとして重要なことを初めて証明し、“Neuro-immune Interaction”という新しい概念を提唱した。
エピジェネティックな修飾因子は、クロマチンの高次構造やDNAのメチル化状態を制御することで細胞の形質決定に重要な役割を担う。Tetタンパク質はDNA修飾を触媒する転写制御因子の一つであるが、最近、DNAメチル化修飾とは別の機序でクロマチン構造や遺伝子転写を調節することも明らかになってきた。しかし、Tetによる免疫・炎症制御の詳細な機序は、ほとんど分かっていない。著者らは、Tet2が樹状細胞やマクロファージなどの自然免疫細胞におけるIL-6発現を負に制御することを示した。Tet2欠損マウスで、野生型に比べてエンドトキシンショックやDSS誘導大腸炎が重症化し、IL-6産生が増加する。またTet2は IL-6特異的転写因子である IκBζの機能を阻害しIL-6産生を抑制すること、HDACを動員してヒストン脱アセチル化を促進し、IL-6 の転写を抑制することを示した。
がんの種類によって、転移しやすい臓器が決まっていること(臓器指向性)は、がん最大の謎の1つである。今回、著者らは、がん転移の臓器指向性は、がん自身が分泌するエクソソーム(癌細胞由来エクソソーム)によって規定されていることを明らかとした。癌細胞由来エクソソーム上に発現するインテグリンがα6β4の場合は肺転移、α6β4の場合は肝転移しやすいこと、さらに、癌細胞由来エクソソーム上のインテグリン発現を減少させることでがん転移が減少することを明らかにしている。これらの結果は、癌細胞由来エクソソーム上のインテグリンの種類を調べることで、がん転移の臓器指向性が予測可能であることを示唆している。
現在がん治療で用いられている抗体医薬品として、乳がん治療のHer2抗体や悪性Bリンパ腫治療のCD20抗体があります。これら抗体はADCC活性による迅速かつ短期間の治療効果を示すと考えられていますが、臨床では抗体治療後も長期にわたって再発がないことが度々報告されています。本論文では、治療初期に起こるADCC活性とその後の免疫記憶に必要なFcγRをそれぞれ同定し、治療抗体におけるFc領域の有用性について述べています。作者らはヒトの免疫記憶が生じるメカニズムとして、まず治療初期に起こるADCC活性にはマクロファージのFcγR3aと治療抗体のFc部の結合が重要なことを示唆し、マクロファージのADCC活性により形成された免疫複合体が、樹上細胞上のFcγR2aへ優先的に結合することで、T細胞の活性化がおこり免疫記憶が生じることを示しました。このことから作者らは今後の治療抗体は目先のADCC活性だけでなく、治療終了後の免疫記憶の誘導性にも注目すべきだと主張しています。
どのようながんに罹患していても、治療効果が高い患者とそうでない患者が存在する。先行研究から、腫瘍局所でIFN-γの産生や細胞傷害性T細胞の集積が観察されると、治療効果が高いことが分かっていた。しかし、どのような因子が治療効果の決定に関与しているのかは不明であった。今回、筆者らはメラノーマ細胞のプロスタグランジンE2(以下PGE2)欠損株を用いて、腫瘍由来のPGE2非存在下では抗腫瘍免疫が惹起されることを示した。また、既存の抗がん剤の奏功率向上を狙い、抗PD-L1抗体及びPGE2産生を阻害するアスピリンの二剤を担がんマウスへ投与したときの効果を観察した。すると、各薬剤の単独投与に比べて二剤併用療法で著しい腫瘍退縮が観察された。これらの結果は、腫瘍細胞が免疫系からの攻撃を逃れるためにPGE2が重要な役割を担っていることを示すと同時に、PGE2の阻害が化学療法の奏功率を高める上で極めて重要であることを示している。
恒常性を維持するために無害な抗原に対する免疫寛容を誘導するのに重要だが、粒子状の抗原に対する免疫寛容の誘導の詳細な分子機構は不明である。本研究では、健常な肝臓と傷害を受けた肝臓における免疫寛容誘導の細胞機構を明らかにすることを目的とした。クッパ−細胞は副刺激分子であるPDL-1の発現が高く、免疫を負に制御するマクロファージである。定常状態において粒子状の抗原を取り込むと抗原特異的なCD4T細胞、特にIL-10を産生するTregを増殖・活性化させることで免疫寛容を誘導する。しかし、肝炎時には活性型のCD80発現が上昇し、クッパ−細胞の数やPDL-1発現が減少する一方、モノサイト由来の炎症性のマクロファージが増加し、この細胞による抗原の取り込みが増える。これにより、クッパ−細胞によるTregの誘導が阻害され、IFN-γを産生するTh1細胞が増加するため、肝炎時に免疫寛容の誘導は抑えられている。
膵臓癌の一種である膵管腺癌は発見が困難な高転移性の癌である。本論文で筆者らは、膵管腺癌から産生されるexosomeが肝臓への転移に重要な肝臓前転移ニッチの形成を誘導することを見出した。膵管腺癌由来のexosomeに含まれているMIFはクッパー細胞に作用してTGF-βの産生を誘導する。肝星細胞はTGF-βシグナル依存的にフィブロネクチンを産生し、F4/80陽性細胞の肝臓への遊走を起こすことで転移ニッチが形成される。更に、膵臓癌が進行した患者の血中exosomeにはMIFが顕著に高いことを見出した。以上のことから、exosome中のMIFが起因となり、膵管腺癌における肝臓の全転移ニッチが形成されることが見出された。
A20はCys103残基を介してRIPK3のリジン5残基をユビキチン化する。このRIPK3のユビキチン化はRIPK1との複合体形成阻害とネクロトーシス抑制に重要である。A20を欠損したT細胞や線維芽細胞ではRIPK1-RIPK3複合体の形成が促進し、ネクロトーシスが亢進する。CD4 T細胞特異的A20欠損マウスでは、多発性硬化症のマウスモデルEAEの進行が抑えられることから、A20は自己免疫疾患の治療標的となりうる。
種々のがん腫瘍内でみられる好酸球の増加は以前から知られていたが、好酸球の腫瘍免疫における機能は不明であった。本論文は、IFN-γやTNF刺激により活性化した好酸球は、CD8陽性T細胞存在下での腫瘍排除に必須であることを明らかにした。腫瘍内の好酸球はCCL5やCXCL9などのT細胞走化性物質を分泌することで腫瘍内へT細胞を誘導した。また、活性化好酸球はマクロファージのM1への分化、腫瘍内血管構造の正常化といった腫瘍内環境の変化を誘導することも明らかにした。これらの結果から著者らは、好酸球ががん治療における新規のターゲットとなる可能性を示した。
がんに集積する免疫細胞は、炎症誘導によってがん転移を促進する働きがある。しかし、免疫細胞が炎症を誘導するメカニズムについては未だ不明であった。本論文ではγδT細胞と好中球の関係性について焦点をあて、γδT細胞がCD8陽性T細胞を抑制する好中球を制御していることを発見した。この報告より、好中球やγδT細胞が転移性がんの治療の新たなターゲットとなることが期待される。
放射線療法はがん治療において、化学療法や手術と並ぶ代表的な治療法の一つである。放射線治療でがんが退縮するメカニズムは、樹状細胞の成熟・活性化に伴いT細胞の抗腫瘍活性が増強されるためと考えられていた。しかし、どのような因子が樹状細胞を成熟・活性化させるのかは明らかにされていなかった。本論文で筆者らは、放射線治療後24時間までの早い段階で補体経路が活性化されることを見出した。さらに、C3 KOマウスを用いて、補体が樹状細胞の成熟・活性化に必須であり、腫瘍特異的な抗腫瘍免疫の惹起に極めて重要であることを証明した。
筆者らは慢性的にLCMV(リンパ球性脈略髄膜炎ウイルス)に感染したマウスにおいて、FcγRを介した抗体のエフェクター機能に重篤な異常が起こることを見出した。通常rituximab投与により起こるB細胞の欠損が、ウイルスに感染したマウスでは起きなかったのである。これはウイルス抗原と抗体の免疫複合体が、FcγRに競合的に結合するためrituximabの抗体機能を抑制してしまうからである。本論文では、抗体治療における抵抗性の新たな原因の一つとして、免疫複合体の関与を示唆している。
リツキシマブ(抗CD20抗体)は、非ホジキンリンパ腫に対する抗体医薬として用いられているが、リツキシマブ抵抗性を示す症例も存在する。本研究では、リツキシマブ抵抗性の要因が、リツキシマブがリンパ腫細胞に結合後に、内在化するためマクロファージによる抗体依存性細胞傷害活性が起こらないためであること、さらに、このリツキシマブの内在化は抗FcγR抗体をリツキシマブと併用することによって阻害できることを明らかとしている。本研究は、リツキシマブ抵抗性の非ホジキンリンパ腫に対する新規リツキシマブ療法の可能性を示唆している。
Ym1、Ym2といったキチナーゼ様タンパクは、Th2免疫応答時に高発現することが知られているが、これらの分子の機能は不明である。本研究において筆者らは、Ym1およびYm2がIL17を産生するγδT細胞の増加させることで、好中球の集積を誘導することを明らかにした。Ym1によって誘導されるIL17および好中球は、宿主に侵入した寄生虫の生存を抑制する一方、代償として肺の傷害を増大した。本研究によってキチナーゼ様タンパクの免疫応答における機能の一端が明らかになった。
抗生物質の投与は腸におけるClostridium difficileを異常に増殖させ腸内フローラの異常を引き起こす。そして異常に増殖したClostridium difficileの毒素により腸管上皮に傷害が引き起こされ、特定の病原性細菌が腸から全身へ移行する。本論文はインターロイキン22が腸から全身へ移行する特定の病原性細菌の排除に重要であることを示している。インターロイキン22は補体系の中心的なタンパク質であるC3の産生を誘導することで、補体系の増強を通して全身性の自然免疫を強化し、全身へ移行した病原性細菌を排除する。
転写因子p53のがん抑制機能は、細胞周期停止・アポトーシス誘導・細胞老化促進に依存すると考えられてきた。本論文で筆者らは、p53がシスチン・グルタミン酸トランスポーターの構成分子SLCA11の発現を抑制することを報告した。この発現抑制はがん細胞におけるシスチン取り込みを阻害し、ROSストレスに伴うフェロトーシスを促進した。本研究によりSLCA11がp53の新たな標的分子であり、p53がフェロトーシス誘導によりがんを抑制する可能性が示された。


